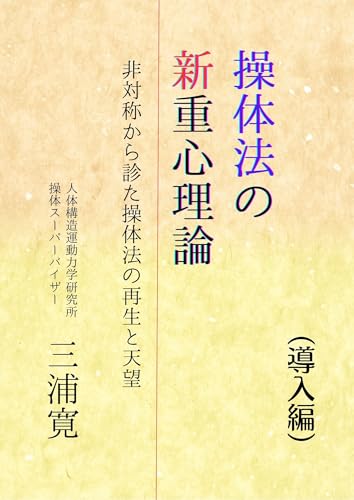2025年11月23日、三浦寛先生の著書が発売になります。
五〇数年前、橋本敬三先生は、三浦先生に言いました。
「自分がやっていることは、六〇年先を行ってるから、今理解されなくても仕方ない」
そこから約六〇年、時代が操体に追いついてきたという予感がします。
奇しくも先の万博で、オムロンがサイニックス理論についてのシンポジウムをやったそうですが、この「サイニックス理論」とは「生体の歪みを正す」にも出てくる『社会進捗曲線』のことです。
キーワードは「自律」。
ちなみに、操体をやっている方で「構造運動力学」「運動構造力学」「構造力学」「運動力学」について、その違いを説明できる方はいらっしゃるでしょうか。
テストに出ます(ウソ)。
まあ、そういうことを勉強探究しているのが我々なんですけどね。
操体のヘンタイだから仕方ないです。
我々はたまにPTの方や、トレーナーと話をする場合、どうも「操体」についての捉え方が違うし、何だか話が噛み合わないことがある、と思っていましたが、彼らが見ている「操体法(っぽいもの。ストレッチとかPNFとほぼ同じ)」と、我々がみている「操体」あるいは「操体法」は、見ている方向が違っていたのです。
また「操体をやっている」という割には、操体のことを「きもちいいストレッチ」(そもそも操体はストレッチではないので、根本的に間違っている)と言っている場合や「難しいトレーニング(と言っている人もいた)」などもあるので、同じ操体実践者の中でも、かなり噛み合わない場合があるわけです。
今回編集を担当してよくわかりました。
さて
元々「構造力学」「運動力学」「構造運動力学」は、橋本敬三先生が使っていた言葉です。
また、第一分析は「サイバネティクス」的な考えであるけれど、晩年の橋本先生の考え方は「サイバネティクス」よりも「元々ダイナミクスよりだったものが一層ダイナミクス的になった(人間を機械や建物ではなく、生命体、命としてまるごと診る)というような流れについては、我々弟子が解説を書いています。
今までも「目線」「快」「皮膚」「連動」を三浦先生が公表した際、多くの操体関係者は「三浦がまた何か言ってるよ」的な反応でしたが、その数年後になると、それが「さも昔からあったような感じ」で「操体の普通」になっているという現場を何度も見てきました。
というわけで、操体も多分あと数年すれば「操体って左重心よね」というのが常識になるのでは?と思っています。
というのは、実際に臨床で結果が出るからです。
この数年、弟子達も実証を積んでいました。
また、この理論が弟子に伝えられたのが2015年頃で、その後あまりにも理論が早く進化したので書籍にするチャンスを逃していたのです。
その間、我々弟子達は「師匠が公表していないことを我々が公表するわけにはいかない」ということで、公には出さずにいました(フォーラムや講習では勿論話題に上っていました)。
この「言いたくても公には言えない」のはもどかしいものですね。
結果を出さなくていい皆さんは、読まないほうがいいかもしれませんし、今までの常識を手放したくない方は、読まない方がいいかもしれません。
実は、東京操体法研究会のメンバーや東京操体フォーラム実行委員の中にも、この理論について行けなかった方もいます。
ただ、操体は第一分析でも第二分析でも、結果は出せます(楽と快を混同している場合は結果は出せないです)。
また、いきなり新重心理論を学ぶよりも、第一分析から歴史順に勉強すると分かりやすいのかな、と私は考えていますので(いきなり新重心理論を学んでいる方もいますが、それはそれなりに大丈夫です)、今後ベーシック講習の中にもプログラムとして入れて行きたいと思っています。